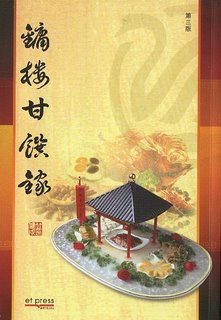マカオの食事情については、マカオ観光協会のサイトで紹介されている。
それにしても「をいをい!」と文句をつけたくなるほど、その紹介は大雑把だ。
たとえばポルトガル料理だが「オリーブオイルや少し辛目の香辛料、ニンニクなどでさっと軽く味付けしたものがポルトガル料理の特徴」と断言してしまう乱暴さに恐れ入る。
マカオにあるポルトガル料理に行ってみればその断言がいかに乱暴で大雑把なものかがわかる。
以前、dancyu誌の取材で訪れた際、同行してくれたマカオ観光局の方はもとより、ポルトガル料理の店を訪れるたび、店のオーナー、マネージャーや料理人から「ポルトガル、といってもいささか広うござんす。南北に伸びた同地の料理は、北と南、さらに、沿岸部と内陸部では異なり、それぞれの地方ごとに味付けも違いますし、独特の料理方法がありますから」と聞かされた。しかも、それぞれの店ごとに「ウチは○○地方の料理が看板です」として、それぞれの地方料理の特徴や代表的な料理方法、料理を教えられた。
マカオでポルトガル料理の代表として紹介されることが多いバカリャウも、店ごとに味、風味は異なる。それは地方色の違いによるからだ、とのことだった。
さらに、先のマカオ観光局のサイトでマカオ料理について「ポルトガル料理に中国、インド、アフリカ等各国料理の美味しさが加わって最終的に出来上がったのがマカオ料理だ。スパイスの効いた港町の料理といったところで、マカオ近海でとれる豊富な海の幸と中国からの野菜をふんだんに使っているのが特徴」、と記されている。
言われてみればなるほど、と思う料理に「アフリカン・チキン」、「カレー・クラブ」がある。スパイシーでホット、しかも、エキゾチックな味と風味が特徴だ。
もっとも、私の観察は異なる。マカオ料理の基本は中国料理、それも広東料理だ。そこに、かつての帆船時代、ポルトガルからマカオに至るまでいたるまでに点在する寄港地の地方料理、その料理方法やエッセンスがマカオにたどり着き、それらが、中国料理、それも主に広東料理に織り込まれ、生み出されたのがマカオ料理ではないか、ということだ。
どうやら、マカオでポルトガル料理を看板する店は、およそ二つに区分されるようである。
経営者、料理人がポルトガル人、もしくはポルトガル系の西洋人、あるいはポルトガルと中国系の混血による店。そして、それ以外のもの、という区分である。それ以外の店で圧倒的多数を占めるのは中国人の経営者、料理人による店だ。
ポルトガル人の経営者、料理人による店は、前述のように、ポルトガルのどこかの特定の地域の料理を看板にし、それを特色としている。
それが、ポルトガルと中国の混血系、中国人の経営者、料理人によるポルトガル料理店では、マカオ料理とされている料理もメニュー並んでいたりする。
マカオ料理を看板にする店も、ポルトガルと中国人との混血系か、もしくは中国人によるものに区分されるようだ。両者にメニュー内容はほぼ共通している。が、その調理、味、風味が異なるのことは、実際に食べてみれば明らかだ。
ややこしい話だが、それが現実なのだ。
「一体、マカオ料理とはどういうものなのか!」という素朴な疑問から、食べ歩きを実践して得た結論である。
ポルトガル料理、マカオ料理を看板にする店も、素材の吟味、調理の技術面から観察すればそれには明らかな差異があり、レベルも異なる。旨い店もあれば、まずい店もあるのが現実だ。
その判断は個人的な嗜好に基づくものではない。素材、調理を吟味、検討しての評価である。
日本で出版されているマカオのガイドブックの食ガイドを信用しないほうがいい、という理由はそうしたことによる。そうした観点からの評価は、皆無に等しい。という以前に、そこまでの追求はなく、ただただ料理店、料理人の意見をそのまま反映したものだからだ。
マカオの食ガイドはもとより、日本の大半の食ガイドにも共通して言えることだ。、
さて、先のマカオ観光局のサイトによる食案内だが、中国料理についての紹介も「北京、四川、広東、上海、潮州などお隣の香港で食べられる中国料理ならほとんど何でも揃っており、中国料理で困ることはない。マカオ人はさっぱりした味を好むので、日本人の好みにもよくあう」と、これまた大雑把だ。
それもまた、ツッコミをいれたくなる紹介である。
というのも、まず、多くの日本人が中国料理に対して持っているのは「中国料理というのは、脂濃くて、味が濃いもの」というイメージであり、それは共通概念として、すでに定着している。
実際、香港などの高級料理店は「さっぱり」、というよりも「あっさり」、つまりは「清淡」な味を特徴としているのだが、多くの日本人客にとってそれはいささか物足りないものであり、それ以前に自身が体験し、認知してきた中国料理とは異なるもの、として拒否反応を示すことが多い、という。
そのため、日本人客の「さっぱり」という要求に対して、現実には味を少々濃い目にする、というのは何度も香港の高級料理店のマネジャーや料理人から聞かされてきた話である。そして、日本人客は、それに納得し、「さっぱりしている!」と感想を述べる、という現実がある。
さて「マカオ人がさっぱりした味を好む」という断言も実に大雑把なものだ。
少なとも私が知り合ったマカオ人のすべてはそうではなかった。つまりすべてが「さっぱり」好みではなかった。
さらに、彼らの言う「さっぱり」の真意は、彼らの日常食を知ってはじめて理解できるものであり、日本で語られる「さっぱり」とは、その意味、真意は日本のそれとは同じものとはいえないものだった。
濃厚な味付けの料理もあって、決してマカオの料理のすべてが「さっぱり」とは思えなかった。
それはマカオ料理店における「カレー・クラブ」や「アフリカン・チキン」の濃厚な味付けからも明らかだ。
そして、マカオの中国料理は、たとえば広東料理など、香港のそれに比べ、穏やかで、素朴な味、風味を特徴している。実際に食べてみれば、それは明らかであり、これまでに触れてきたとおりだ。
しかも、中国料理はマカオ料理に比べ、淡白なもの味、風味を持つものが多い。
つまり「中国料理といえば脂っこくて、濃い味付けのもの」と言う認識をもつ多くの日本人にとっては、むしろ、物足りなさを感じるのではないだろうか、というのが私見である。
残念ながら、マカオの四川料理、上海料理、潮州料理を食べる機会にはめぐまれていないが、住民の大多数を占めるのが広東人であり、特有の嗜好をもっていることや、同じ広東人が大多数を占める香港でのそれら各地の料理を思い浮かべれば、その現実は推して知るべし、といえるのでないだろうか。
画像はセナド広場。さらに、フランシスコ・ザビエル教会にあった、ザビエルの像である。